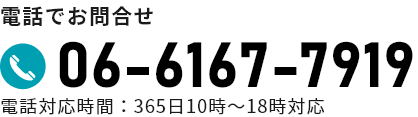お墓じまいが増えている?
■ はじめに|「お墓じまい」という言葉、よく聞くようになったと思いませんか?
近年、「お墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
テレビや雑誌、インターネットのニュースでも取り上げられ、
実際にご相談いただく件数も年々右肩上がりに増加しています。
でも実際のところ、本当にそんなに増えているの?
なぜ今、多くの人が「お墓じまい」を考えるようになったの?
そんな疑問にお応えするために、この記事では、
お墓じまいが増えている背景やその理由、実際に選ばれている供養のあり方について、わかりやすく解説していきます。
初めて「お墓じまい」という言葉に触れた方も、
「そろそろ考えるべきかな…」と思い始めた方も、ぜひ最後までご覧ください。
■ なぜ今、お墓じまいが増えているのか?【5つの主な理由】
「お墓じまい」が増えている背景には、現代社会ならではのさまざまな事情があります。
ここでは、実際にご相談いただく中で多くの方が口にされる、主な理由を5つに整理してご紹介します。
1. 少子化・核家族化の進行
昔は「長男が墓を継ぐ」のが当たり前の時代でしたが、
現代では子どもがいなかったり、娘だけの家庭も多くなっています。
また、子ども世代が結婚・転勤などで遠方に住んでおり、お墓を継ぐことが現実的でないというケースも増えています。
2. 都市部への人口集中と地方の過疎化
地方にあるお墓が「遠くて通えない」「維持ができない」といった悩みもよく聞きます。
高齢の方にとっては、長距離の移動や管理そのものが大きな負担になっているのが実情です。
3. 経済的な負担の軽減
お墓の維持には、年間の管理費や法要費用など継続的な出費がかかります。
将来にわたってその費用を負担し続けることに不安を感じ、
費用のかからない永代供養などへ移行する目的で墓じまいを選ばれる方も少なくありません。
4. ライフスタイルや宗教観の変化
「お墓は必要」と考える人がいる一方で、
近年は「無宗教」「供養は気持ちが大事」といった考えを持つ方も増えています。
形式にとらわれず、自分たちのライフスタイルに合った供養を選ぶ流れの中で、墓じまいが選択肢の一つになっています。
5. 永代供養や納骨堂など、新しい選択肢の登場
昔に比べて、現代はお墓に代わる供養のスタイルが多様化しています。
-
お寺が永代にわたって供養してくれる「永代供養」
-
室内で天候に左右されない「納骨堂」
-
自然に還ることを重視した「樹木葬」など
これらの選択肢が身近になったことで、
「墓じまい=供養をやめること」ではなく、「新たな供養の始まり」として前向きに受け入れられつつあります。
■ 墓じまいを選んだ人の声(実例紹介)
実際に墓じまいをされた方々は、どんな悩みを抱えて、どんな思いで決断したのか?
ここでは、一休堂にご相談いただいたお客様の実際の声をもとに、3つの事例をご紹介します。
【事例①】娘だけの家族で、将来を考えて早めの決断
〈大阪府・50代女性〉
「うちは娘しかいないので、いずれ誰が墓を見るのか…とずっと気になっていました。
まだ元気なうちに、永代供養に切り替えておけば娘にも負担をかけずに済むと思い、墓じまいを決意しました。
相談して本当に良かったです。心がスッと軽くなりました。」
【事例②】遠方で管理が難しく、年に一度のお参りも大変に
〈東京都・60代男性〉
「実家のお墓が九州にあり、毎年の帰省費用や移動が年々負担になっていました。
子どもも首都圏で生活しており、将来的に無縁墓になるのではという不安が…。
墓じまいで納骨堂へ移し、都内から気軽にお参りできるようになって安心しました。」
【事例③】兄弟間の話し合いで全員が納得できた供養の形へ
〈京都府・40代男性〉
「本家としてずっとお墓を守ってきましたが、弟や妹と相談し、みんなが無理なく供養を続けられる方法を考えました。
結果として、永代供養を選んで墓じまいに。離檀などの対応も一休堂さんが丁寧にサポートしてくれたので、安心して進められました。」
■ 増加の裏にある“不安”や“トラブル”も
墓じまいを検討する人が増えている一方で、不安や戸惑い、実際のトラブルに直面する方も少なくありません。
「やってみたいけど…大丈夫かな?」というお声の背景には、次のような問題があります。
家族・親族間で意見が分かれることも
「お墓を守ってきたのに勝手に決めていいのか?」
「まだ親が健在なのに縁起でもないのでは?」など、
家族内・親戚内で意見のすれ違いが起こるケースがあります。
✅ 対策:
-
早めに話し合いの場を設ける
-
「供養をやめる」のではなく「新しい供養に切り替える」ことを丁寧に説明する
-
必要なら第三者(専門家)に間に入ってもらう
お寺や霊園との関係で悩むケースも
-
檀家を辞める「離檀」の際に、離檀料の支払いを求められることがあります
-
「断りづらい」「ご住職に何と言えばいいかわからない」という声も多く聞かれます
✅ 対策:
-
まずは丁寧にお礼と感謝を伝える
-
離檀料は気持ちとしての“お布施”であり、明確なルールはない
-
不安な場合は一休堂のような第三者が間に立って交渉や対応サポートを行うことも可能です
業者選びで後悔しないために
「安くお願いしたつもりが、追加費用がかかった」
「作業が雑だった」「連絡がつかない」といった業者トラブルも報告されています。
✅ 対策:
-
見積もり内容が明細で提示されているかを確認
-
墓じまいの実績が豊富な業者を選ぶ
-
できれば複数社を比較検討するのがベストです
一休堂では、複数業者の見積りを比較できる無料サービスを提供しています。
事前にこうしたリスクを知っておけば、墓じまいは決して難しいものではありません。
次のセクションでは、「墓じまい=供養の終わりではない」ことについて、前向きな視点からお伝えします。
■ 墓じまいは「ご供養の終わり」ではない

「お墓をしまう」=「供養をやめる」と誤解されることがありますが、
実際には墓じまいは“新しい供養のかたち”への移行であり、供養そのものが終わるわけではありません。
むしろ、多くの方が墓じまいを機に「今の自分たちに合った供養の方法」を見つけています。
墓じまい後も、心のこもった供養は続けられる
墓じまいのあと、多くの方が選んでいるのが以下のような供養方法です:
-
永代供養
→ 寺院や霊園が責任を持ってご供養を続けてくれる安心のスタイル -
納骨堂
→ 都市部でもアクセスしやすく、天候を気にせずお参り可能 -
樹木葬・自然葬
→ 自然に還るという考え方に共感する方に人気 -
手元供養
→ 遺骨の一部を自宅で供養する、近年注目の方法
どれも「ご先祖様への感謝」や「手を合わせる気持ち」を大切にしながら、
現代の暮らしや価値観にフィットする供養の方法として支持されています。
大切なのは「今の家族に合った供養」を選ぶこと
お墓を守り続けることが難しくなったとしても、
ご先祖様を想う気持ちや、ご家族の心のつながりが途切れるわけではありません。
むしろ、
-
無理のない場所に遺骨を移すことで、もっとお参りがしやすくなる
-
次の世代に負担をかけず、気持ちよく引き継げる
というように、「これからの供養」を前向きに整えるチャンスでもあります。
一休堂では、墓じまい後の供養もトータルサポート
「墓じまいしたあと、どこに遺骨を納めればいいの?」
「永代供養ってどう選べばいいの?」といった不安にも、一休堂が丁寧にご対応します。
関西圏の永代供養寺院・納骨堂など、信頼できる提携先の中からご希望に合う供養先をご紹介できます。
■ まとめ|時代と共に変わる供養のかたち

かつては「お墓を守るのが当たり前」だった時代から、
今は多様な家族のかたち・ライフスタイル・価値観に応じた供養の選択が求められる時代へと変化しています。
墓じまいの増加は、時代の流れに合った“前向きな選択”
「お墓をしまう」というとネガティブに捉えられがちですが、
実際には、
-
無縁墓になる前にきちんと供養をしたい
-
家族や子どもへの負担を軽くしたい
-
自分たちの暮らしに合った供養を選びたい
という、思いやりと前向きな気持ちからの選択であることがほとんどです。
ご先祖さまへの感謝の気持ちは、かたちが変わっても続けられる
大切なのは、「お墓を持っているかどうか」ではなく、
ご先祖さまを想う気持ちをどう大切にしていくかということ。
お墓じまいは、単なる“お墓の片づけ”ではなく、
今の暮らしに合った“新しい供養の形”へとつなぐ架け橋でもあります。
墓じまいを考えたら、まずは気軽に相談から
「いつかは必要になるかも…」「うちも考えた方がいいのかな?」
そんな気持ちが芽生えた今が、最初の一歩のタイミングです。
一休堂では、
-
無料相談
- 写真を送るだけ!最短2日で簡単見積り
-
現地確認〜施工〜供養先紹介までの一括サポート
をご用意し、不安なく進められる環境を整えています。
📩 お墓じまいのご相談はこちら
📞 お電話:06-6167-7919(受付時間:9時~18時)
🌐 問い合わせ フォーム→こちらから(LINEからも24時間受付中)
墓じまいは、家族や故人にとって大切な決断です。
正しい知識を持ち、後悔のない選択をするために、今すぐ行動を始めましょう!
未来のために、ご家族のために、そしてご先祖さまのために。
あなたらしい供養のかたちを一緒に見つけていきましょう。