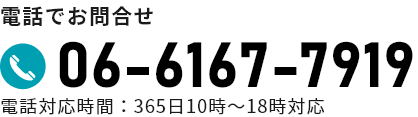墓じまいでゾッとした話、全部、実話です。

「墓じまいでそんなことになるなんて、思いもしませんでした——」
これは、実際に一休堂に寄せられたお客様の声です。
親族との関係、菩提寺とのやりとり、費用のトラブル…。
“ちゃんとやったつもり”が、思わぬすれ違いで大きな問題に発展するケースが少なくありません。
このコラムでは、実際にあった“墓じまいでゾッとした話”をもとに、後悔しない進め方を解説します。
あなたの身にも、起こるかもしれません——。
🕯️ :これはすべて“実際にあった話”です。
──「まさか、墓じまいが原因でこんなことになるなんて…」
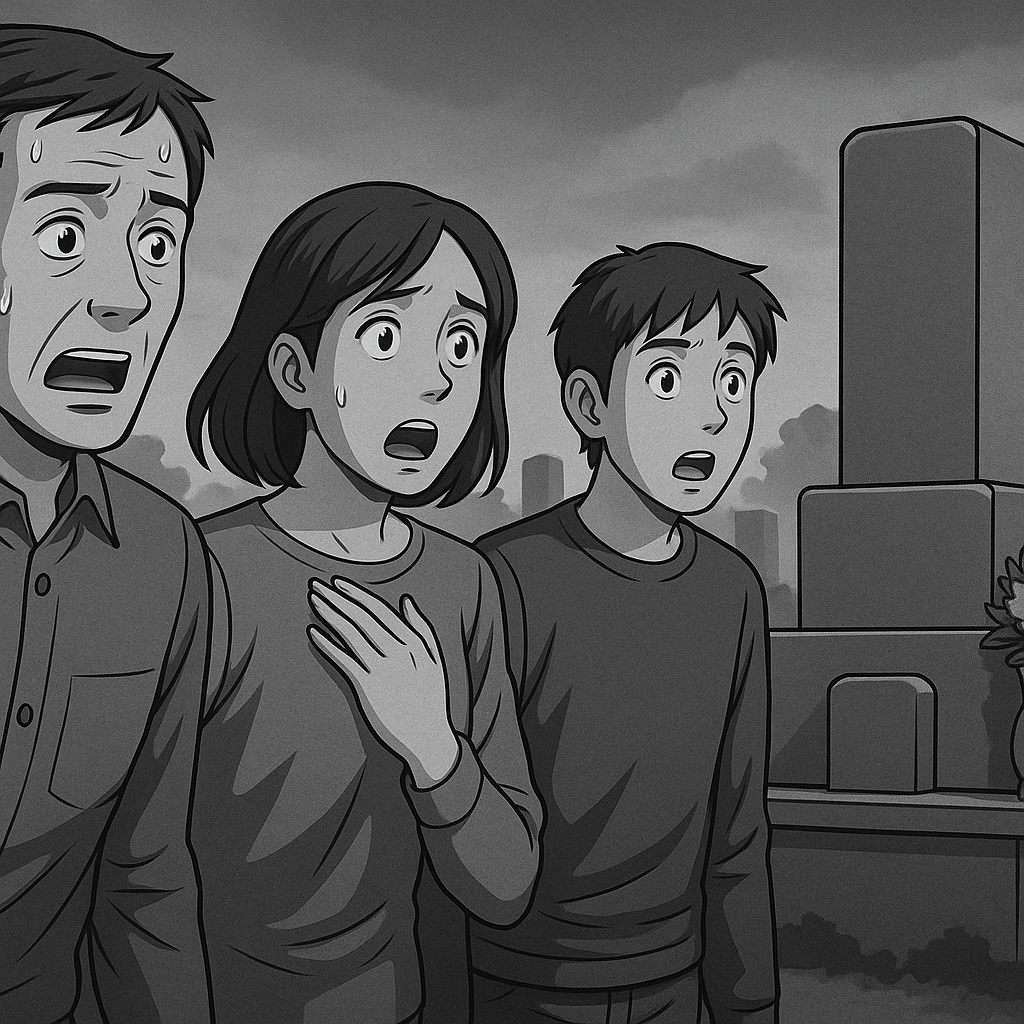
🧓 ケース1|親に黙って墓じまいをしたら、兄と絶縁寸前に
東京都・50代女性の例。
仕事と育児に追われるなか、実家の墓が気がかりだったというAさん。
「父も亡くなり、母も高齢。もう誰もお墓参りに行けてないし、今のうちに墓じまいを」と、兄に相談せず一人で進めたのが始まりでした。
ところが、手続きが終わった数日後、兄から電話が。
「なんで勝手にそんなことしたんだよ!」
感情的な言い合いになり、以後、連絡は一切取れなくなってしまったといいます。
Aさんは「悪いことをしたとは思ってないけど…もっと丁寧に相談すればよかった」と後悔の念をにじませていました。
🧑🦳 ケース2|「まだ大丈夫」と言っていた親が急逝し…間に合わなかった墓じまい
大阪府・40代男性の例。
「親も元気だし、墓じまいなんてまだ早い」と思っていた矢先のこと。
突然、父親が倒れ、亡くなりました。
いざ進めようとすると、お墓の管理名義、改葬許可証の取得、離檀交渉…どれも何から手をつけていいか分からず、心身ともに疲弊。
さらに、「なんでお父さんに相談しておかなかったんだ」と、親戚から非難を受ける場面も。
「タイミングを逃すと、墓じまいは一気に重くなる。元気なうちに相談しておくべきだった」と語ってくれました。
🧘♂️ ケース3|菩提寺に相談せず閉眼供養を進めた結果…
京都府・60代女性の例。
実家の仏壇とお墓を整理するために、ネットで見つけた供養業者に依頼。
手際よく閉眼供養を済ませ、墓じまいの手続きも完了。
…のはずでした。
1ヶ月後、菩提寺から電話が入りました。
「うちを通さずに閉眼供養とは、どういうことですか?」
関係は悪化し、離檀料の請求や親族からのクレームが相次ぐ事態に。
「よかれと思ってやったことが、結果的にご先祖に対して失礼な形になってしまった」と、今も気に病んでおられるそうです。
📌 どれも特別な話ではありません
今回ご紹介したのは、どれも特別な状況にあった人の話ではありません。
ごく普通のご家庭で、ごく自然な流れで起きた出来事です。
-
「まだ大丈夫」と思っていた
-
「ちゃんとやったつもりだった」
-
「まさか、こんな風になるとは…」
これらの共通点が、ゾッとする結末を生んでいるのです。
⚠️ :「ゾッとした」のは、こんな落とし穴だった
── “手続き”ではなく“人間関係”が、墓じまいの落とし穴です。

墓じまいのトラブルでよく聞く言葉があります。
「まさか、あの人があんな反応をするなんて…」
そう、“ゾッとする瞬間”は、書類の不備や段取りミスではなく、**人間関係の“すれ違い”や“思い込み”**から起きることがほとんどなのです。
🧩 落とし穴①:親族間の“温度差”
たとえば、「自分は墓じまいが当然」と思っていたのに、
兄弟や親戚は「そんな話、聞いてない」「勝手に決めたの?」と猛反発。
特に多いのが「遠方に住んでいて現実感がない人」と「地元に残っていた人」で意見が真っ二つに割れるケース。
話し合いの場を持たずに進めてしまうと、「なんで相談してくれなかったの?」という**“感情のズレ”が大きな溝**になります。
🧩 落とし穴②:お寺とのやりとりを甘く見た
「お寺は、手続きをすればすんなり応じてくれる」と思っていませんか?
現実には、
-
「うちは閉眼供養を外部には依頼できません」
-
「離檀料が必要です」
-
「先祖代々の墓をそんな簡単に…」
など、宗派・お寺ごとの考え方の違いに直面して困惑する人も少なくありません。
しかも、電話一本では済まないことも多く、
菩提寺との信頼関係や段取りの誤解から、精神的に疲れてしまう方も。
🧩 落とし穴③:「費用の話」が後回しにされがち
墓じまいでは、閉眼供養・お布施・改葬費・業者への処分料など、複数の費用が発生します。
しかし、多くの方が「なんとなく話しづらいから…」と金額面をぼかしたまま進め、
あとで「誰が払うの?」「高すぎる!」「知らなかった!」と揉めることに。
とくに親族間で費用を折半する場合は、最初に“誰がどの範囲を負担するのか”を明確にしておかないと、後の関係に大きな亀裂が入ります。
🧠 知識不足と「自分だけで何とかしよう」が招くすれ違い
これらの落とし穴に共通しているのは…
-
事前に知っていれば防げた
-
相談していれば対処できた
-
早めに話し合っていれば揉めなかった
ということです。
📌 墓じまいは、手続き以上に“人との調整力”が求められる場面。
でも、それを**「全部一人で抱えよう」としてしまうと、必ずどこかでズレが生じます。**
☑️ “自分は関係ない”と思っていませんか?
墓じまいに関わるトラブルは、決して特別な人だけの話ではありません。
どれも、ごく普通のご家庭で、誰にでも起こり得ることばかりです。
「あのとき、ちゃんと話し合っていれば…」
「もう少し調べておけば、こんなことには…」
そんな後悔の声が、一休堂にも数多く届いています。
💥 :墓じまいでよくある“トラブル事例”5選
── 誰にでも起こりうる、でも「防げたはず」のトラブルとは?

「墓じまいは慎重に進めましょう」と言われても、実際にどんなトラブルがあるのかイメージがつかない方も多いかもしれません。
ここでは、実際に一休堂に相談があった中でも、よくある5つの事例をご紹介します。
いずれも「自分には関係ない」と思っていた方が体験した、ごく普通のご家庭のリアルな話です。
⚠️ トラブル①:兄弟間で“責任の押し付け合い”が勃発
「私は末っ子だから」「長男がやるべき」
こんな声から始まった墓じまいの話し合いが、いつしか険悪ムードに。
誰が動くのか?誰が費用を出すのか?
明確に決めないまま進めようとすると、最終的に「なんで私ばかり…」と不満が爆発します。
📌 解決のポイント:最初に“役割”と“費用”を共有しておくこと
⚠️ トラブル②:「勝手にやったの!?」と親戚からの苦情
遠方に住んでいた娘さんが、実家の墓じまいを一人で完了。
そのことを後日知った叔父・叔母から「なぜ相談もなく勝手に!?」と非難の連絡が相次ぎました。
相談しにくい関係だったとしても、“連絡すべき相手”はリストアップしておくべきです。
📌 解決のポイント:事前に「報告」だけでも入れておくと印象がまったく違う
⚠️ トラブル③:閉眼供養を飛ばして、お寺から厳しい指摘
墓じまいの作業そのものに気を取られ、閉眼供養をすっかり忘れていたケース。
お寺からは「ご先祖への供養が抜けている」と厳しいお叱りが入り、改めて供養を依頼する羽目に。
📌 解決のポイント:必ず「魂抜き(閉眼供養)」のタイミングと場所を確認しておく
⚠️ トラブル④:費用の分担でもめる
見積もりをもとに「折半でいいよね?」と兄弟で進めていたのに、
最終的に追加費用や交通費がかかり、
「そこまで払うつもりじゃなかった!」と揉めるパターン。
特に、後から加算される費用(例:永代供養費・戒名返納料など)は事前共有が必須です。
📌 解決のポイント:総額の目安と“誰が何を出すか”を明確にする
⚠️ トラブル⑤:業者に丸投げして“後悔”が残る
「プロに任せれば安心」と思っていたら、
事前説明が不十分なまま墓石が撤去され、
「あっという間に終わってしまった…」と気持ちの整理がつかず、後悔の声も。
📌 解決のポイント:供養の立ち会い・報告方法・タイミングを事前にすり合わせておく
🧘♂️ トラブルの裏側には、いつも“説明不足”と“相談不足”がある
紹介した5つの事例に共通しているのは、**「早めに話し合っていれば防げた」**という点です。
-
「きっと分かってくれているはず」
-
「後で説明すればいいや」
-
「自分が動けばなんとかなる」
そうした“思い込み”が、結果的にトラブルを生んでしまうのです。
🌱 :でも大丈夫。“知っていれば防げる話”なんです
── トラブルを回避できた人たちが、最初にやっていたこと
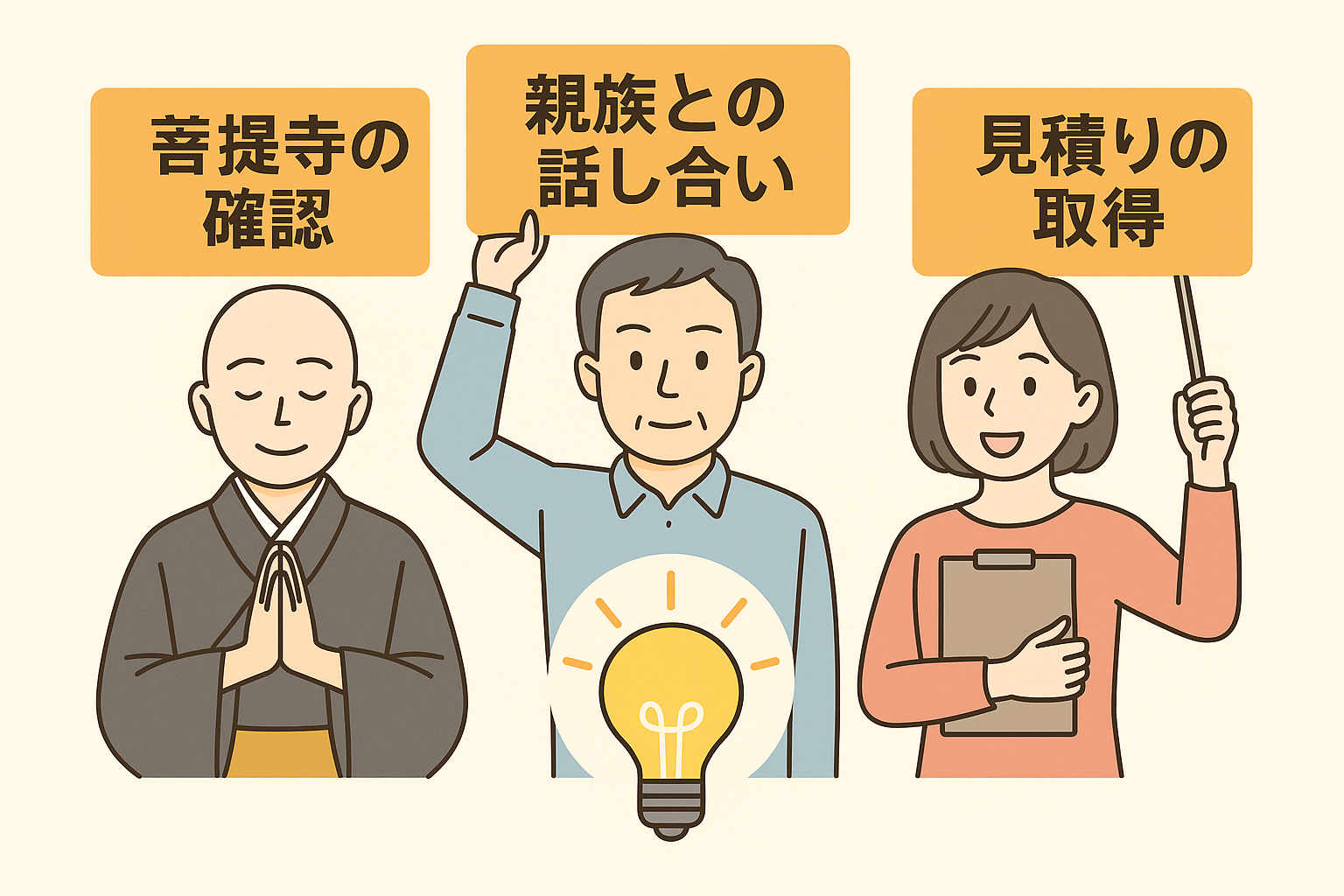
ここまで読んで「やっぱり墓じまいって難しそう…」と感じた方もいるかもしれません。
でも、安心してください。
ご紹介したようなトラブルは、事前に「正しい順序」と「必要な知識」を知っていれば、ほとんどが防げるものなのです。
実際に一休堂にご依頼いただいた方々の多くも、最初は不安や戸惑いを感じながらも、
少しずつ情報を整理し、納得のいくかたちで墓じまいを終えています。
✅ STEP1:まずは「家族で共有」から始める
墓じまいは、誰かひとりの判断で進めると後で必ずズレが生まれます。
まずは「こういうことを考え始めている」と、家族に話題として出すことから始めましょう。
たとえばこんな一言からでも十分です:
「最近、墓じまいっていう選択もあるって知って…」
「お父さんたちがいない未来のことを、少しずつ考えないとね」
話すきっかけをつくるだけで、その後のスムーズさが大きく変わります。
✅ STEP2:「相談すべき人」をリストアップしておく
-
菩提寺(檀家関係や供養の流れ)
-
親族(兄弟・叔父叔母・継承者候補)
-
墓の名義人(改葬許可証の取得者)
このように、事前に関わる人を洗い出し、軽くでも連絡を取っておくことが肝心です。
黙って進めることが「ラク」なようで、後から火種になることもあります。
✅ STEP3:「お寺とのやりとり」は早めに確認
お寺によっては「閉眼供養はうちの僧侶でなければならない」「離檀料が必要」など、
独自のルールを持っている場合があります。
📌 特に多いのは「あとから言われて困る」パターン。
先に「こんな方向で考えているのですが…」と、丁寧に相談ベースで伝えておくことで、
信頼関係を損なわずに話を進めることができます。
✅ STEP4:見積もりと費用分担は「紙」で見える化
「だいたい折半で」「出せる範囲でいいよ」と口約束で進めると、
金額のズレや、見解の食い違いが後からトラブルになります。
-
お布施・離檀料
-
墓石の撤去・処分費用
-
永代供養料や納骨堂の使用料
これらを一覧にし、「誰が何を負担するか」まで書き出しておくと、あとで揉めにくくなります。
✅ STEP5:一人で抱えない。専門家に頼るという選択肢も
「家族に話すのが気まずい」
「お寺との距離感が難しい」
「そもそも何を聞けばいいか分からない」
そんな方こそ、墓じまいに詳しい専門業者に相談するのがおすすめです。
一休堂では、
-
ご家族との話し方
-
お寺への連絡文の例
-
トラブルになりやすいポイント
なども含めて、やさしく丁寧にご案内しています。
🧘♀️ 「まだ何も決まっていなくても大丈夫です」
一休堂に寄せられるご相談の半分以上が、
「まだ決めてないけど、どうしたらいいですか?」
という段階です。
誰でも最初は不安で当然。
でも、正しい順番で進めれば、“穏やかな墓じまい”は実現可能です。
🫶 :私たちは、こうして安心して終えました。
── “ゾッとする話”を他人事にしなかった家族たちの体験

ここでは、実際に「墓じまいの一休堂」にご相談・ご依頼いただいた方々の声をご紹介します。
トラブルを回避し、安心してお墓の整理を終えることができた方々の“リアルな体験”です。
👩 60代女性/東京都
「一人で抱え込まずに、最初から相談してよかったです」
実家の墓は地方にあり、遠方の兄とは連絡が取りづらい状況。
「親族と揉めたくない。でも、今のうちに整理しておきたい…」と不安ばかりが募っていました。
最初はLINEで気軽に相談しただけ。
でも、担当の方がこちらの状況をじっくり聞いてくださり、
「まずは家族への伝え方から一緒に考えましょう」とアドバイスしてくれました。
おかげで兄にも納得してもらえ、閉眼供養から墓じまいまで段取りよく、心もスッキリした形で完了できました。
👨🦳 70代男性/大阪府
「菩提寺とのやり取りも、全部サポートしてもらえました」
私たち夫婦はもう高齢で、子どもも遠方。
自分たちの代で墓をしまう決意をしたものの、「お寺に何と言えばいいのか…」というのが最大の悩みでした。
一休堂さんに相談したところ、
宗派やお寺の事情に応じた話し方やタイミングまで細かく教えていただきました。
お布施の相場や閉眼供養の流れも丁寧に説明してくれたので、安心して“最後のご挨拶”ができたと感じています。
👩👧 50代女性/京都府
「母と対立しかけたけど、“プロの一言”で救われました」
「墓じまいなんて縁起でもない」と猛反対していた母。
話すたびに空気が悪くなり、「もう無理かも…」と諦めかけていました。
一休堂の担当者の方に相談すると、
「反対されて当然です。まずは“手放す”のではなく、“未来の選択肢のひとつ”として伝えてみては?」と、言葉の選び方から丁寧にサポートしていただきました。
数週間後、母から「そろそろ考えた方がいいかもしれないね」と一言。
あの瞬間は忘れられません。
🧩 なぜ「一休堂に相談してよかった」と言われるのか?
それは、一休堂がただの“業者”ではなく、
お客様一人ひとりの背景や感情に寄り添うパートナーであることを大切にしているからです。
-
「誰に何を話せばいいのか?」から一緒に考える
-
菩提寺・親族との関係に応じた伝え方を提案
-
費用・スケジュールも丁寧に見える化して説明
-
しつこい営業は一切なし
📌 どんなに小さな疑問でも、「それ、みなさん最初に悩まれますよ」と受け止めてもらえる安心感があります。
🧘♀️ “やってよかった”と思える墓じまいに
-
「やっと肩の荷がおりました」
-
「最後まで家族で納得して進められました」
-
「気持ちよくご先祖を送り出せた気がします」
そんな声が、少しずつ届いています。
🧭 :まとめ|“ゾッとする話”を、自分ごとで終わらせないために
── 後悔しないために、今できることを

ここまで「墓じまいでゾッとした話、全部、実話です。」をお読みいただきありがとうございました。
トラブルに直面した方々の共通点は、「ちゃんとやったつもりだった」「そんなつもりじゃなかった」という思いと、
その裏にある**“知識不足”や“話し合い不足”**でした。
でも一方で、実際に安心して墓じまいを終えられた方々の多くは、
- ✅ 家族と早めに共有し、
- ✅ お寺や親族と丁寧に対話し、
- ✅ 必要な知識を事前に確認し、
- ✅ わからないことを専門家に相談していました。
つまり、事前に「知っているかどうか」「誰かに相談したかどうか」だけで、墓じまいの印象は大きく変わるのです。
✅ 墓じまいは“情報戦”でもある
-
閉眼供養はいつ?どこで?誰に?
-
菩提寺への伝え方は?離檀料は?
-
お布施はいくら?のし袋は?
-
墓石撤去や永代供養の費用は?
-
家族や親族にどう伝えればいい?
これらのひとつでも「あいまいなまま」進めると、
思わぬ誤解やすれ違いがトラブルにつながる可能性があります。
✅ “今すぐ決めなくてもいい”という選択
「いますぐ墓じまいをするかどうか」は、実は重要ではありません。
大切なのは、“正しい準備の仕方”を知っておくこと。
-
お父さんが元気なうちに、話せることはありますか?
-
ご自身が将来、子どもに残す不安を減らしたいと感じていますか?
-
今のうちに、プロの意見を聞いておくだけで安心できますか?
そのすべてに、「はい」と言えなくても大丈夫です。
まずは「相談だけしておこうかな」――それで十分なんです。
☎ 墓じまいの一休堂では、こんなご相談が寄せられています
-
「菩提寺との関係が不安で…」
-
「親にどう話せばいいか分からなくて」
-
「そもそも何から始めたらいいんでしょうか?」
-
「何も決まってないけど、相談だけできますか?」
▶ すべて、LINEや電話でご相談OKです。
▶ 営業は一切ナシ。ご家族に合った進め方を一緒に考えます。
🧘♂️ “あのとき相談してよかった”と思える未来のために
墓じまいは、ご先祖さまへの感謝とともに、
「次の世代へ、負担を残さない」という優しさのかたちでもあります。
あなたが今、少しでも「気になっている」なら――
それは、きっと“動き出すタイミング”です。
📩 最後に、ひとこと
「まだ大丈夫」と思っている“今”こそが、準備を始めるいちばんのチャンスです。
まずは、LINEや電話で、あなたの想いや状況をお聞かせください。
わたしたち一休堂が、“ゾッとする話”にならないように、全力でサポートいたします。
📞墓じまいの一休堂に、まずは“相談だけ”しませんか?
🗣️ 墓じまい、こんなお悩みはありませんか?
-
「親にどう切り出せばいいかわからない…」
-
「菩提寺との関係が気まずくなりそうで不安」
-
「何から始めればいいか、正直わからない」
-
「決めていないけど、まず話だけ聞いてみたい」
そんなときは――
墓じまいの専門スタッフが、あなたの不安や状況を丁寧にお伺いします。
✅ 墓じまいの一休堂のご相談窓口(無料)
📩 LINEでかんたん見積り・相談する(24時間受付/返信は営業時間内)
- ▶ QRコードまたは下のボタンから登録・送信OK
 ▶ お墓の正面、背面、左右の側面の4方向から撮影した写真をLINEで送信するだけ📷
▶ お墓の正面、背面、左右の側面の4方向から撮影した写真をLINEで送信するだけ📷
簡単にお見積りが可能です
📞 電話で話したい方はこちら(年中無休9:00〜18:00)
- ▶ 電話番号:06-6167-7919
- ▶ 状況を聞いた上で、最適な進め方をご提案いたします
- ▶ 強引な勧誘や営業は一切行っておりません
🌐ホームページからのお問合せはこちら
- ▶お問合せフォームは[こちら]
💬 ご相談者さまの声
「“まだ何も決まってなくて…”という状態でも、すごく丁寧に聞いてもらえてホッとしました」
「不安だった気持ちが、電話のあとにはスッと晴れていました」
🧘♀️ 最初の一歩は、“話す”だけでも構いません
墓じまいは、あなた一人で悩む必要はありません。
一休堂が、あなたとご家族の想いに寄り添いながら、
後悔のない選択をサポートさせていただきます。